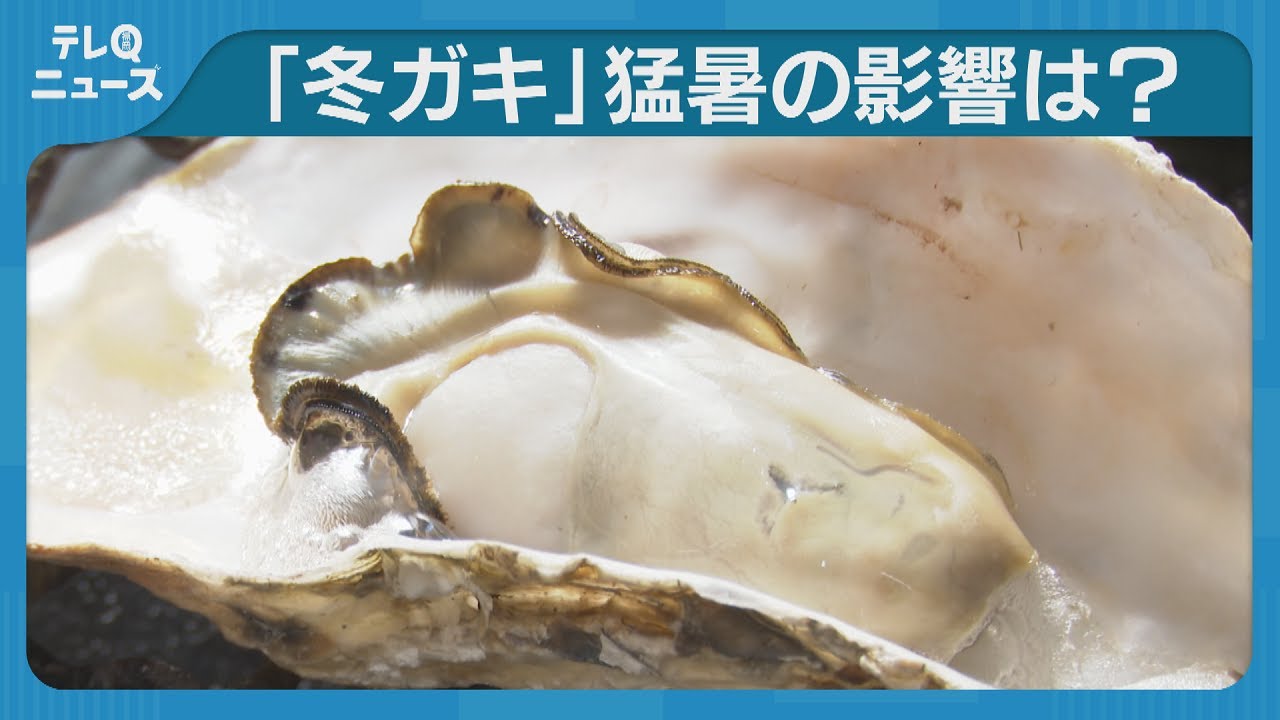真牡蠣100g
2025年11月の平均価格458円
最高値467
最安値316
- 物価高騰📈ランキング
- 56全181項目調査中コロナ禍前からの上昇率133%
カキ(牡蠣)は水揚げされる期間が限られているため、調査月は1月〜3月、10月〜12月となっています。
日本国内で流通しているカキは真牡蠣と岩牡蠣が2大品種です。
真牡蠣は、太平洋のアジア沿岸を原産地とすることから太平洋牡蠣とも呼ばれ、日本で一般的に食用として流通している牡蠣で、国内市場に出回る真牡蠣はほぼ100%が養殖で、主に太平洋側の浅瀬を中心に養殖されています。真牡蠣の養殖は歴史が非常に古く、ヨーロッパでは2500年以上前の紀元前1世紀から、日本では1673年に安芸の国(現在の広島県)で真牡蠣を増産できるようになったとされます。その後、1900年代前半に現在の主流の養殖法である垂下式養殖法が神奈川県で開発され、日本各地へ普及し、国内での真牡蠣の養殖が飛躍的に増大し、現在では品種改良も進み、通年出荷も可能になり国内牡蠣消費量の自給率は80%以上あります。
岩牡蠣は、日本全国に分布していますが、日本海側の3m~15mの海底に生息している夏が旬の天然物がよく収穫されています。天然の岩牡蠣は素潜り漁のため、希少価値が高いのが特徴です。養殖の岩牡蠣も、1992年に島根県隠岐島において技術が確立され、日本各地へ広がりをみせていますが採算割れしている現状が多いとされます。
カキ(牡蠣)の高騰・値上がり理由
- 過酷な労働環境下での牡蠣養殖業に従事する人材が減っているのが直接の原因。牡蠣の養殖は外国人技能実習生への依存が高く、むき身に加工する打ち子の人手不足から生産が追いつかず、供給量が減少し、需給逼迫から高騰した。
動画で知る
データで見る
カキ(牡蠣)の国内自給率・輸入割合
カキ(牡蠣)の国内自給率・輸入割合は、自給率が80%、輸入が20%で、自給率が圧倒的に上回っています。
カキ(牡蠣)の国内水揚量 (2021年)
| 1位 | 広島県 92,827t (58.5%) |
|---|---|
| 2位 | 宮城県 22,335t (14.1%) |
| 3位 | 岡山県 14,798t (9.3%) |
| 4位 | 兵庫県 10,148t (6.4%) |
| 5位 | 岩手県 6,208t (3.9%) |
| 6位 | 北海道 4,175t (2.6%) |
| 7位 | 三重県 1,944t (1.2%) |
| 8位 | 福岡県 1,709t (1.1%) |
| 9位 | 長崎県 1,037t (0.7%) |
| 10位 | 香川県 980t (0.6%) |
| ... | |
| 総水揚量 | 15万8,789t |
真牡蠣100gの平均価格(相場)
| 2025年平均 | 439円 |
|---|---|
| 2025年11月 | 458円 |
| 2025年10月 | 467円 |
| 2025年3月 | 414円 |
| 2025年2月 | 428円 |
| 2025年1月 | 430円 |
| 2024年平均 | 427円 |
| 2024年12月 | 433円 |
| 2024年11月 | 437円 |
| 2024年10月 | 460円 |
| 2024年3月 | 408円 |
| 2024年2月 | 411円 |
| 2024年1月 | 414円 |
| 2023年平均 | 404円 |
| 2023年12月 | 418円 |
| 2023年11月 | 427円 |
| 2023年10月 | 441円 |
| 2023年3月 | 378円 |
| 2023年2月 | 379円 |
| 2023年1月 | 378円 |
| 2022年平均 | 362円 |
| 2022年12月 | 383円 |
| 2022年11月 | 390円 |
| 2022年10月 | 391円 |
| 2022年3月 | 329円 |
| 2022年2月 | 336円 |
| 2022年1月 | 341円 |
| 2021年平均 | 341円 |
| 2021年12月 | 348円 |
| 2021年11月 | 356円 |
| 2021年10月 | 364円 |
| 2021年3月 | 318円 |
| 2021年2月 | 324円 |
| 2021年1月 | 333円 |
| 2020年平均 | 344円 |
| 2020年12月 | 339円 |
| 2020年11月 | 348円 |
| 2020年10月 | 363円 |
| 2020年3月 | 334円 |
| 2020年2月 | 338円 |
| 2020年1月 | 344円 |
| 2019年平均 | 345円 |
| 2019年12月 | 349円 |
| 2019年11月 | 360円 |
| 2019年10月 | 376円 |
| 2019年3月 | 316円 |
| 2019年2月 | 330円 |
| 2019年1月 | 339円 |
真牡蠣100gの最高値は2025年10月に467円、最安値は2019年3月に316円で最高値と最安値の価格差は151円ありました。最新調査月である2025年11月現在の平均価格は458円です。コロナ禍前と比較した場合に133%平均価格が上昇しました。
出典
- ・小売物価統計調査 1132 カキ - 真牡蠣・むき身・100g。
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003421913